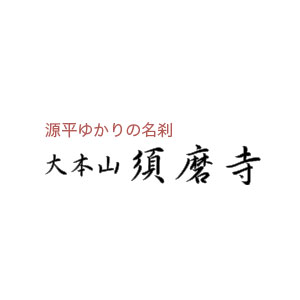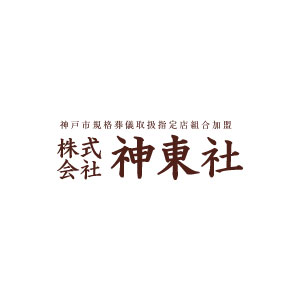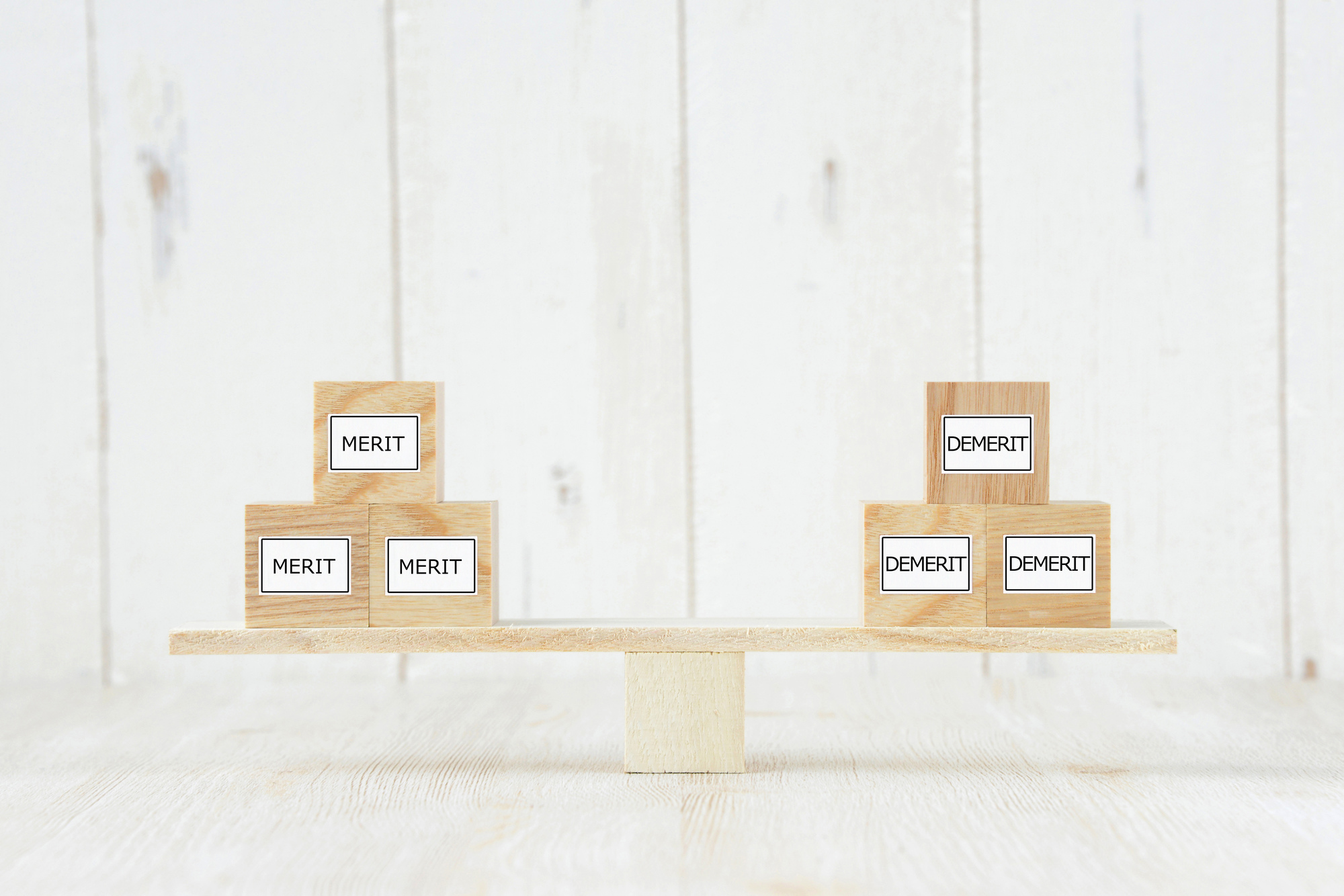納骨するのに適切なタイミングは?納骨の手順も解説!

納骨は、たいていの方が慣れない儀式ですので、準備や手順などわからないことばかりです。お通夜・葬儀・初七日と多くの法要を行い、次は納骨。しかしいつ・どのように納骨すればよいのか、何を準備するのかなど、とても不安だと思います。そこで今回は、納骨のタイミングや手順、費用などについてわかりやすく説明します。
納骨する時期に決まりはない
納骨とは、故人を死後の世界の新しい家に落ち着いてもらうための儀式で、納骨をいつ行う・いつまでに行うなどの決まりはありません。遺族の方が話し合ったうえで、適当な時期に行えばよいのです。
ただ、納骨をする具体的な時期というものはあるので、そちらを参考にしてみましょう。
納骨のタイミングとして一般的に選ばれやすいのは?
納骨を行うタイミングにとして、よく選ばれているのは、次の5つの時期です。それぞれを順に説明します。
四十九日
故人が亡くなって49日目に行う四十九日法要が納骨をする初めのタイミングです。仏教の世界では、故人が完全に現世から離れ、あの世へ行く日とされており、納骨には最適の時期だとされています。また、四十九日は、親族が集まって法要を行うことが多いため、納骨も一緒にする方が、参列者にとって都合がよいという理由もあります。
しかし、四十九日法要のときに納骨できるのは、すでにお墓がある場合、もしくはお墓の準備が整っている場合に限ります。故人が亡くなった後にお墓の手配をしているのであれば、四十九日の納骨には間に合いません。また別の時期にした方がよいでしょう。
百箇日
亡くなってから100日目の百箇日のタイミングで納骨を行う方も多いです。百箇日は「卒哭忌(そっこくき)」と呼ばれ「泣いて(哭いて)暮らす日からはもう卒業し、日常に戻る」日という意味を持っているため、遺族が心の整理をつけるタイミングとしても納骨にはよい時期です。
新盆
故人が亡くなってから初めてのお盆を新盆(にいぼん)と言います。新盆に納骨をすることもよいのですが、この時期は僧侶にとってもっとも忙しい時ですので、早めに相談をしておくほうがよいでしょう。
ちなみに、四十九日前にお盆を迎えるのであれば、次の年のお盆が新盆になります。季節的にはもっとも暑い時期にあたりますので、参列者の体調にも考慮が必要です。
一周忌
故人が亡くなって1年たった一周忌に納骨する方も多くいいます。お墓の準備が必要な方や気持ちの整理がつかなかった方にとっても、充分な時間がとれ、落ち着いてくるころでもあるので、区切りとして一周忌に納骨することで遺族が新しい生活を歩むことができるのではないでしょうか。
三回忌
故人が亡くなって2年目の命日が三回忌です。2年目なのになぜ三回忌なのか、疑問に思う方もいるでしょう。それは、亡くなった日を1回目の忌日と考えるからです。亡くなって1年目の命日が2回目の忌日、そして亡くなって2年目の忌日が3回目の忌日となります。納骨の時期に決まりはありませんが、遅くとも三回忌までには納骨をした方がよいでしょう。
いつまでもそばに遺骨を置いておきたいと思う方もいるでしょうが、それでは、故人の魂がいつまでたってもあの世へ行くことができません。故人が安らかに眠れるように、きちんと納骨してあげましょう。
納骨式・納骨の手順
実際に納骨をするときの準備と手順については、次の通りです。
納骨する場所を選ぶ
もともとお墓があり、そこに納骨する場合は問題ありませんが、新しく納骨場所を選ぶなら、時間的な余裕が必要です。墓地と墓石を一から準備するには、墓石の準備も含め最短でも3か月はかかります。納骨堂や樹木葬なら、空いていれば比較的早く決めることができますが、墓石を建立したいのなら、やはり3か月ほどの期間が必要です。
墓石に字を彫ってもらう
すでにあるお墓に納骨する場合も、墓石に故人の名前を彫ってもらわなければなりません。場合によっては数週間かかるかもしれませんので、早めに依頼しておきましょう。
納骨先や菩提寺に連絡する
納骨先が決まったら、墓地管理者や菩提寺などへ連絡をします。その際、納骨をする日にちの調整もしなければなりません。時期によっては、希望の日に行えないこともあるので、できるだけ早く連絡をしましょう。
参列者へ連絡する
納骨の法要に参加する親族の都合と菩提寺との調整で決めた納骨の日時を改めて親族に連絡をします。もし近い家族だけで納骨を行う場合も、家族だけで行うことと、納骨の日を親族に伝えた方がよいでしょう。何も連絡がないと、不満を持ったり、トラブルになったりすることもあるので、親族との付き合いには細心の注意をはらってください。
埋葬許可証の用意をする
納骨するときには、埋葬許可証が必要です。埋葬許可証とは、火葬許可証(死亡届と同時に申請し、発行される)に火葬場の証印や火葬した日時が記入されたものを言います。火葬場の方が、骨箱に入れてくれていることもあるので、確認してみてください。
埋葬許可証がないと納骨をしてもらえませんので、しっかりと保管しておいてください。万一紛失してしまったら、できるだけ早く役所で再発行してもらいましょう。
ちなみに、分骨する場合は、火葬場に申し出て分骨証明証を発行してもらわなくてはなりません。分骨証明証無しで勝手に分骨すると死体遺棄罪に問われる恐れがあるので、気を付けてください。
供花・供物・塔婆・お布施などの準備をする
納骨の際にお供えするお花やお菓子、果物などの準備とともに、塔婆やお布施の準備も必要です。塔婆とは、卒塔婆とも言い、亡くなった人の追善供養のためにお墓に建てる木の板のことです。菩提寺や法要を行っていただく寺院にお願いすれば準備してもらえます。費用は3,000~5,000円程度が相場です。住職に法要をしてもらう場合には、お布施として3~5万円程度を用意してください。
会食そのほか参列者へのおもてなしの準備をする
もし必要なら、法要後の会食の準備をします。参列者の負担にならないように、納骨場所からあまり離れていない場所を選んだほうがよいしょう。
納骨当日の持ち物
納骨をする日に必要な持ち物は、埋葬許可証・墓地使用許可証(霊園から発行される)・印鑑・塔婆・お布施・お供え物・数珠などです。
納骨式の流れ
宗教・宗派・地域によって多少の違いはありますが、一般的な納骨式の流れは、
・喪主(施主)のあいさつ
・僧侶の読経
・納骨
・僧侶の読経
・焼香
・会食
以上のようになります。喪主(施主)のあいさつでは、参列者へのお礼の言葉や遺族の近況報告、会食の用意がある場合はその旨を簡潔に話します。2度目の読経には、故人を供養するためであり「納骨経」といわれています。
焼香は、喪主(施主)から遺族、近親者、知人の順になります。参列者の人数にもよりますが、納骨式は30分~1時間程度で終わることがほとんどです。
まとめ
納骨を行う時期に、決まりはありません。しかし、故人があの世で安らかに過ごすため、遺族が気持ちの区切りをつけるためには、あまり遅くなることはよくありません。納骨することで、遺族は葬儀が本当に終わったという気持ちになると思いるため、適当な時期を選んできちんと納骨しましょう。お墓がある場合と新しく作る場合で違いはありますが、どちらの場合でも遺族が落ち着いて納骨ができる無理のない時期を選んでください。この記事が少しでもお役に立てれば、幸いです。