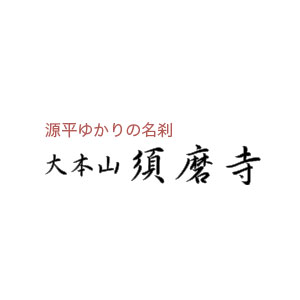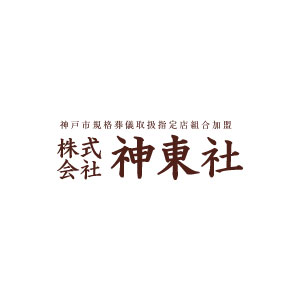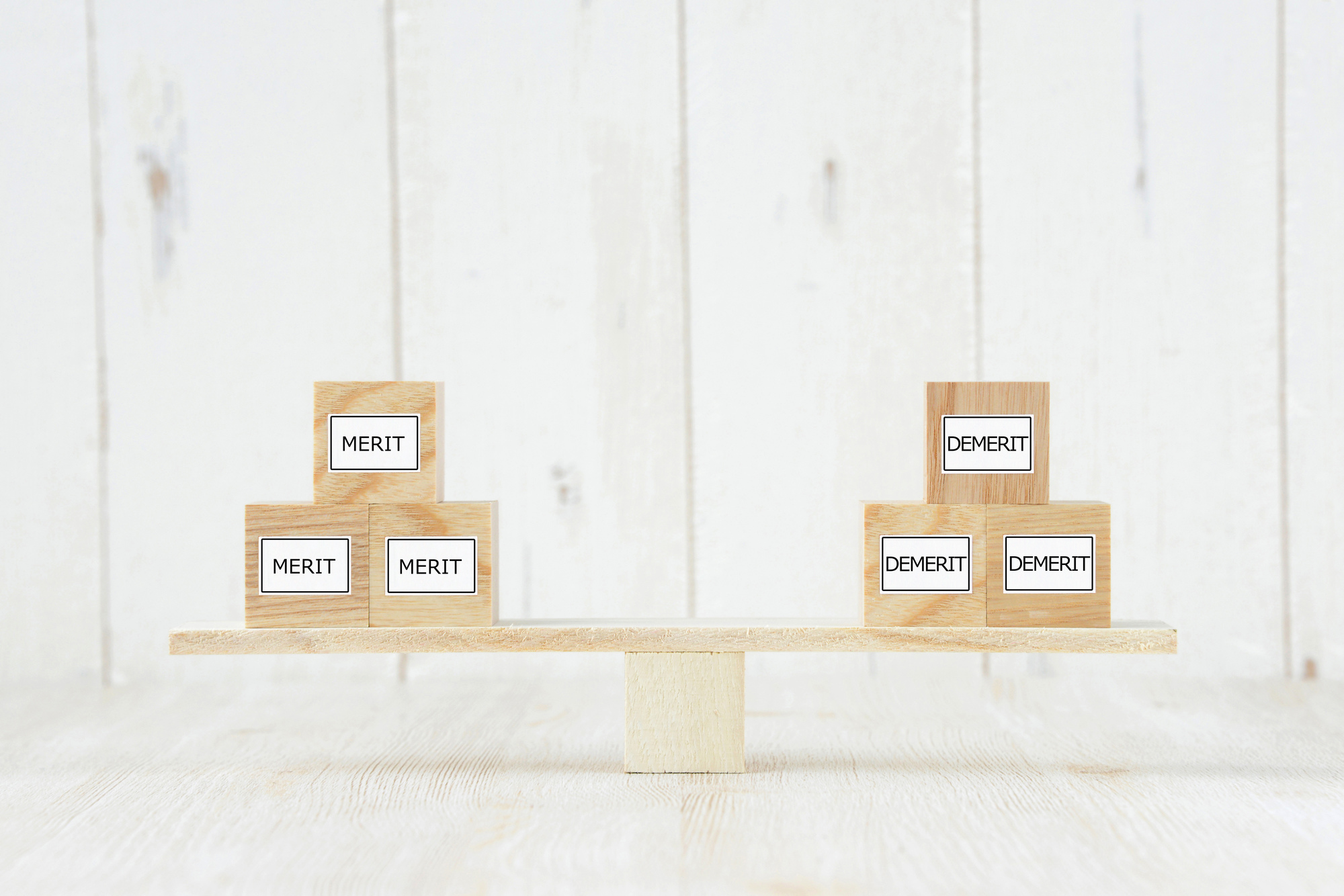納骨堂とお墓の違いとは?それぞれのメリット・デメリット

1人用または核家族用として、注目を集めるようになってきた納骨堂。「先祖代々受け継いでいくお墓と何が違うの?」「そもそも納骨堂って何?」という疑問をお持ちの方のために、この記事ではお墓と納骨堂の違いについて解説します。それぞれのメリット・デメリットを考慮したうえで、自分たちにとって最適な供養方法を選びましょう。
納骨堂とは
納骨堂とは、「遺骨を預けて保管してもらう場所」のことです。建物の中にあることが多く、その多くはロッカー型になっています。かつてはお墓に入れるまで一時的に預ける方が多かったのですが、近年では宗教や宗派は自由なところが多いこととお墓より安価に済むことで、納骨堂を本格的な埋葬場所として選ぶ方も多いです。そのため最近ではロッカー型をはじめ、神社が経営する神棚型や位牌型、仏壇型、墓石型、機械型、合葬・合祀型など、実にさまざまな種類の納骨堂が誕生しています。
お墓とは
墓地に墓石を建立し、遺骨や遺体を埋葬して供養するために祀る場所がお墓です。江戸時代に檀家制度が確立し、「先祖供養」という概念が定着したことがきっかけで誕生しました。お墓にはいくつか種類があり、いずれも都道府県の許可を得て開設されていますが、各自治体が運営する公営墓地、企業または宗教法人が運営する霊園(民間墓地)、寺院の檀家たちが埋葬される寺院墓地、共同墓地などのみなし墓地の4つがあります。
納骨堂とお墓の違い
肝心な、納骨堂とお墓の違いについて解説します。埋葬先として選ぶ場合、納骨堂とお墓でどんな風に変わるのでしょうか?
収蔵期間が異なる
一番大きいのは収蔵期間の違いでしょう。納骨堂は「遺骨を預けて保管してもらう場所」となるので、一定の期間を定めて契約し供養してもらうことが多いです。期間終了後は管理者によって合祀され、引き続き永代供養を受ける流れとなります。これに対し、お墓は永代使用料や年間管理費を支払うことで、その区画を半永久的に使用する権利を得られます。
参拝方法の違いは?
線香を立て、花を供えたり掃除をしたりしてお参りをする。ごく一般的なお墓参りのイメージですが、実はこれはお墓特有の参拝方法です。納骨堂は、屋内にあることから火気厳禁とされ、電気式のろうそくを用いる場所が多いです。また、お参りできる時間も、納骨堂のルールに則って決められています。
宗派の多様性について
お墓、とくに寺院墓地などでは、檀家であることが必須です。そのため、どうしてもそのお墓に入りたい場合は、改宗が必要になる場合もあります。これに対し、民間企業などが運営している納骨堂の場合は、宗派を問いません。寺院が運営していても、納骨堂に限っては檀家になる必要がなく、「宗派も問わない」と定めているところもあります。
それぞれのメリット
納骨堂とお墓の違いがわかってきたところで、それぞれのメリットについて見ていきましょう。
納骨堂のメリットは?
まず、納骨堂は駅の近くなど、交通の便がよい場所にあることが多いです。また、屋内にあるため、高齢者や体の不自由な方でも通いやすく、天候を気にせずお参りできる点が最大のメリットといえるでしょう。また、一定の契約期間後は合祀されるため、後継者がいなくても安心です。さらに、共用部分は管理者が掃除をしてくれるので、お参りの度に掃除をする必要がありません。
お墓のメリットは?
お墓には先祖代々の墓誌が建てられていたり、墓石の裏にはそこで眠っている人の名前が刻まれていたりします。そのため、「先祖がそこに眠っている」という実感を得やすいです。また、納骨する人数にも制限がないため、何人でも安置できます。何より、掃除して墓石に水をかけ線香をあげるといった伝統的なお墓参りができるのです。
それぞれのデメリット
納骨堂とお墓のメリットはわかりましたが、それではデメリットについてはどうでしょうか?よい所があれば当然悪いところもあるので、考慮する材料にしてみましょう。
納骨堂のデメリットは?
場所にもよりますが、ロッカー式の納骨堂では1人または2人までの遺骨を安置するタイプが多いです。また、機械型だと遺骨が搬送され、ロッカー型だと「ロッカーの前で手を合わせる」といった形式でお墓参りすることになります。そのため、伝統的なお墓参りと比べて雰囲気が出ないなど、違和感がある方もいるようです。さらに契約期間後は合祀され、他の方たちの遺骨と一緒に供養されるため、合祀後は取り出せません。
お墓のデメリットは?
草むしりを含め、お墓は自分で敷地内の掃除をする必要があります。少なくとも、手入れや管理には手間がかかるといえるでしょう。また墓石も高額ですが、将来的には経年劣化もあるため、メンテナンス費用も大変です。業者に依頼した際は、1~10万円もの費用が発生します。そして、お墓は子々孫々と継承していくものなので、継承者が必要です。さらに、お墓を永続的に使用するためには年間管理費が発生しますし、寺院の檀家になっている場合は法要にも参加する必要があります。
納骨堂とお墓の違いについて、それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説してきました。納骨堂は屋内にあり継承者が不要、管理も共用部の掃除をしてくれるので楽であること。そして、お墓は自分たちで管理する必要があるけれど、ご先祖様を身近に感じやすく伝統的なお墓参りができることから、自分たちのライフスタイルに合わせて選べることがわかりました。それぞれの特徴を考慮したうえで、ベストな供養方法を選びましょう。